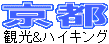寂光院 じゃっこういん
寂光院は聖徳太子が593年(推古2年)に用明天皇の菩提を弔うために建てたのがはじまりで、 平清盛の娘である建礼門院が平家一門の冥福を祈りながら侘しい生活を送ったという尼寺です。大原バス停から寂光院までは1.1kmです。道標が整備されているので迷うことはありません。 大原バス停前の信号を左折して川沿いの小道を歩いていきます。 田園風景を眺めながらのんびり歩いていくと、朧(おぼろ)の清水という平家物語ゆかりの泉があります。 やがて茶店や漬け物屋などが並んで賑やかになると寂光院に着きます。
 大原バス停 |
 左折 |
 川沿いの小道 |
 田園風景 |
 右折 |
 寂光院へ |
石段を上って門をくぐると本堂です。2000年に不審火で本堂が全焼し、本尊の六万体地蔵菩薩立像も焼損しましたが、胎内仏などが残り、2005年に本堂が再建されました。 境内には平家物語ゆかりの汀の池、汀の桜、諸行無常の鐘、豊臣秀吉が寄進した雪見燈籠などがあります。 本堂奥の四方正面の池には三段の滝があり、それぞれの段の音色が合奏するかのように作庭されているそうです。
 石段 |
 汀の池 |
 豊臣秀吉寄進の雪見燈籠 |
 本堂 |
 四方正面の池 |
| 京都の寺社 | |